柔軟性の大切さ
● 股関節・肩甲骨の柔軟性が重要
 ボールが狙ったところとずれたときの方が力のあるボールが投げられる
ボールが狙ったところとずれたときの方が力のあるボールが投げられる
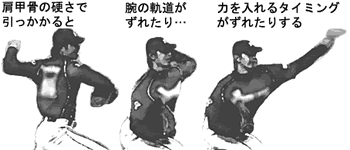 肩甲骨が硬くて思ったとおりに動かしづらい部分があると、腕の軌道がずれたり、無理に思い通りに動かそうと無意識に力が入ったりします。
肩甲骨が硬くて思ったとおりに動かしづらい部分があると、腕の軌道がずれたり、無理に思い通りに動かそうと無意識に力が入ったりします。
● 腕の軌道がずれるケース
肩甲骨が硬くて、引っ掛かりがある場合は、無意識に引っ掛かりを避けようするため、腕の軌道がずれます。
腕の軌道がずれることで、肩甲骨の引っかかりはさけられ、気持ちよく腕が振れるかもしれませんが、狙ったところにボールはいきません。
狙いからずれたときに気持ちよく投げられ、強い球がいく選手はこういった理由です。
● 力を入れるタイミングがずれるケース
人間は、ずーっと力を入れていると、瞬間的に大きな力を発揮することはできません。
できるだけリリースの直前は腕の力が抜けていたほうがはるかに大きな力を発揮できます。
しかし、体の硬さのためにリリースの前に無意識に力が入ってしまうと、「力を入れるタイミング」がずれてしまいます。
無理に狙ったところに投げようとすると、ぎこちない腕の振りになって、思うようにボールが投げられなくなるのはこういった理由からです。
 ボールが狙ったところとずれたときの方が力のあるボールが投げられる
ボールが狙ったところとずれたときの方が力のあるボールが投げられる皆さんの中に下記のような悩みを持った選手はいませんか?
「高めや内側に抜けたときのほうが力のあるボールが投げられる」
「無理に狙ったところに投げようとすると、球がおじぎしてしまう」
「力まずに、ムチのようにしなる投げ方ができない」
「いろいろ考えているうちに、投げ方がわからなくなってしまった」
しかし、これらのうまくいかない原因は「無意識の動き」が悪さしている場合が多いのです。
投げ方がわからなくなってしまった選手の多くは、「無意識の動き」を意識しすぎて、本来意識できない部分まで頭で考えてしまったことが原因です。
無意識の動きが悪さする要因の一つとして、「柔軟性」があげられます。
特に野球の場合、股関節・肩甲骨の柔軟性は大切です。
股関節の硬さは、下半身の動きを制約し、開きが早くなったり、開きを抑えようと上半身に余計な力が入ったりします。
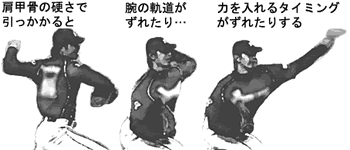
● 腕の軌道がずれるケース
肩甲骨が硬くて、引っ掛かりがある場合は、無意識に引っ掛かりを避けようするため、腕の軌道がずれます。
腕の軌道がずれることで、肩甲骨の引っかかりはさけられ、気持ちよく腕が振れるかもしれませんが、狙ったところにボールはいきません。
狙いからずれたときに気持ちよく投げられ、強い球がいく選手はこういった理由です。
● 力を入れるタイミングがずれるケース
人間は、ずーっと力を入れていると、瞬間的に大きな力を発揮することはできません。
できるだけリリースの直前は腕の力が抜けていたほうがはるかに大きな力を発揮できます。
しかし、体の硬さのためにリリースの前に無意識に力が入ってしまうと、「力を入れるタイミング」がずれてしまいます。
無理に狙ったところに投げようとすると、ぎこちない腕の振りになって、思うようにボールが投げられなくなるのはこういった理由からです。
● 動的な柔軟性と静的な柔軟性の違い
動きを止めた状態での可動域の大きさを静的な柔軟性といいます。一般的に柔軟性といえば、こちらをさすことが多いでしょう。
しかし、スポーツにおいては、常に体が動いていますので、「動きの中での可動域」がパフォーマンスに大きく影響します。
陸上で日本記録を出すようなトップアスリートの中には、静的ストレッチは一切行わず、動的ストレッチのみという徹底した選手もいるくらいです。
動きの中での柔軟性にも着目をして、パフォーマンスを向上させましょう。
動きを止めた状態での可動域の大きさを静的な柔軟性といいます。一般的に柔軟性といえば、こちらをさすことが多いでしょう。
しかし、スポーツにおいては、常に体が動いていますので、「動きの中での可動域」がパフォーマンスに大きく影響します。
陸上で日本記録を出すようなトップアスリートの中には、静的ストレッチは一切行わず、動的ストレッチのみという徹底した選手もいるくらいです。
動きの中での柔軟性にも着目をして、パフォーマンスを向上させましょう。
● MFTのおすすめ
野球体操 (ベースボールマガジン社)
(ベースボールマガジン社)
須田 和人(著), 比佐 仁(監修)
柔軟性を高めるために大変参考になる本です。
肩甲骨や股関節をただ柔軟にするだけではなく、野球に必要な動きと連動するように柔軟性を高めていくためのノウハウが詰まっています。ぜひ、日々のウォーミングアップ等の参考にしてください。
須田 和人(著), 比佐 仁(監修)
柔軟性を高めるために大変参考になる本です。
肩甲骨や股関節をただ柔軟にするだけではなく、野球に必要な動きと連動するように柔軟性を高めていくためのノウハウが詰まっています。ぜひ、日々のウォーミングアップ等の参考にしてください。
次のページで「目線によるずれ」について説明します。

