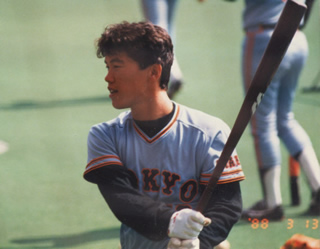キャンプ使用球場
久し振りの更新になってしまいました。
すみません。
サマーキャンプまでもうすぐです。
今年も北海道・東北・関東を中心に申し込みをいただいております。
ありがとうございます。
詳細は下記にてご確認ください。
http://mft.jp/school_top.htm
今年のキャンプでは・・・
生活環境や習慣の違いにより
子供たちの生活習慣が一昔前とは違ってきています。
実際にどれほど大きな影響があるかは計り知れませんが
スポーツの世界ではマイナスの要因が多々あります。
我々はこのポイントを見過ごすことはできません。
体の問題
拇指球を使えず、踵(かかと)と外側体重が「開き」の原因を作っています。
股関節・足首の動きの悪さが野球技術に直結しています。
たとえば裸足になる機会はどうでしょう?
以前は体育の時間や運動会は裸足でした。
おそらく足指は今の時代よりは使っていたと思われます。
心の問題
親子を中心とした事件が多発しています。
ルールやマナーを守れない人が増えています。
自己中心的発想ではなく、他人を思いやりながら
自立に向かった心の育成を目指します。
技術の問題
テクニックに走りすぎていて、土台作りが疎かになっています。
ボールの握り・ボールさばき・バットコントロール
立ち方などを中心に、自身の能力を最大限に引き出せるように
良い習慣を身に付けさせます
その他
親が教育熱心で塾や習い事で大忙しで遊ぶ暇がありません。
携帯電話・ゲーム機・パソコンなどの電子機器の普及により
夜遅くまで触っている子供が増えています。
睡眠時間の減少に伴い、子供たちは常に疲れている状態です。
こんな時代背景の中で、私達が野球を通じて子供達に伝えられる事は?
今回のサマーキャンプのテーマもここにあります☆
【体の改善】
拇指球を意識させる → 地下足袋を履かせます!
目の疲労を取る → 動体視力をアップさせます!
パワーポジションを意識させることにより
正しい身のこなしを習得します。
【心の改善】
団体生活の中で、他人を思いやったり、助け合ったりすることにより
リーダー的役割のできる子供の育成を目指します。
どう考えどう行動するか?
生活習慣を見直す「きっかけ」の場にします。
【技術の改善】
「真っ直ぐ立つこと」
そして「立てること」を目指します。
すべてが野球の技術向上に繋がります。
【最後に・・・】
「野球の楽しさ」「仲間の大切さ」「感謝の心」を
伝えるキャンプを目指します。