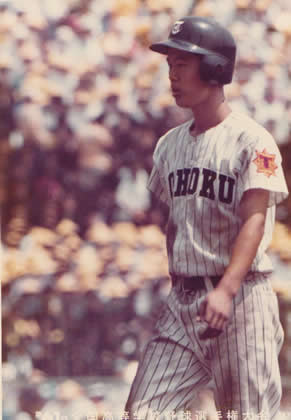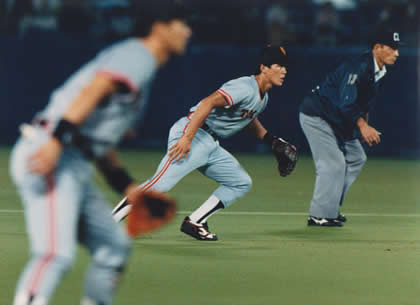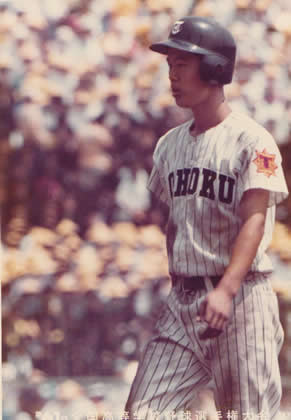子供の成長には厳しさも大切である。
しかし厳しくすることと、グランドで怒鳴る行為は
まったく別の物なのに、履き違えている大人があまりにも多い。
厳しさとは何か?
声を掛けずに見守ることであり
自分でできることは自分でやらせることである。
子ども自身に気付かせ、それをいかに継続させるか。
そこに厳しさを私は求めたい。
被災地に入った皆さんが口を揃えて発言する言葉に
「励まそうと思って行ったのに、逆に勇気をもらいました」
そのことは、素晴らしい経験であり、世の中の人に伝えるべきだ。
お世話をする側の想いと、お世話になる側の感謝の想いが一致すると
そこに素晴らしい空気が生まれ、「お陰様で」が生まれる。
そこに気がつくと楽しさは倍増し、一気に加速して行く。
野球のグランドではどうだろう?
「子供たちに野球を教えてやっている」
おそらく何かのボタンが、ずれていると思う。
怒鳴っている人達は、間違いなく
「教えてやっている」が強調される。
子どもと純粋に向き合っている人達は
「教える立場なのに、子供たちから教えてもらう方が多い」
そこに気がつくことができる。
グランドで、大人も子どもも
「お陰様で」と本気で思えたら、そこに集まっている人達は
もの凄いスピードで成長するはずだ。
その環境を作るのも大人。
そして壊しているのも大人。
怒鳴られている子ども達は、何も悪くない。
思いっきりボールを投げればいい。
思いっきりバットを振ればいい。
それが「野球」だ!